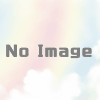一般職と専門職の「待遇の壁」— エンジニア・デザイナー採用で企業が直面する課題
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れを背景に、多くの企業でITに関するエンジニアやデザイナーといった専門職の需要が急速に高まっています。一方で、これまで主に一般職(事務・営業・企画職など)を中心に構成されてきた企業では、専門職の採用や定着に苦戦しているという現実があります。
その背景には、一般職を前提とした社内制度や待遇が、専門職に適していないという構造的な課題があります。
給与体系のギャップ:専門職の「市場価値」が反映されない現実
一般職と専門職では「価値の基準」が異なる
一般職は多くの企業で共通した職務内容・評価制度が確立されており、比較的横並びの給与体系が構築されています。一方、エンジニアやデザイナーは専門スキルと市場での希少性により、給与水準が大きく異なるのが一般的です。
しかし、企業によっては「社内バランス」の観点から、一般職と同じ給与テーブルで専門職の報酬を決めてしまうケースが見られます。これは結果として、市場から見て「魅力のないオファー」となり、優秀な人材を逃す要因となります。
専門職の市場価値に見合わない給与提示 → 他社へ流出
社内の横並び意識が障害に → 給与改定の足かせ
既存の専門職のモチベーション低下 → 離職リスク増加
年功序列からの脱却:スキルベース評価の必要性
特に日本企業に根強い「年功序列型給与体系」は、専門職にとって大きな障害となります。技術職は年齢ではなく「今あるスキル」と「アウトプット」で評価されるべき職種であり、それに応じた給与設定が求められます。
新卒でもハイレベルなスキルを持つ人材は、高く評価されるべき
→ 海外やスタートアップでは当たり前の考え方
年齢や勤続年数ではなく、職種ごとの専門性・成果に応じた報酬制度へ転換
→ フェアな評価がモチベーションを引き上げる
スキルアップに応じたスピーディな昇給制度
→ 専門職人材の成長を阻害しない設計が必要
業務環境の差:一般職基準の設備では専門職の力を活かしきれない
業務内容の違いが「必要な設備・環境」を分ける
一般職が主にメール・文書作成・表計算を中心に業務を行うのに対し、エンジニアやデザイナーは、複雑な処理を行うソフトウェアやツールを日常的に使用します。そのため、必要とされる機器・ソフトウェア・ネットワーク環境はまったく異なります。
しかし、全職種共通のIT環境を前提とした企業では、専門職の業務効率が著しく下がる状況が生じています。
低スペックPCの支給 → 開発・デザイン作業の生産性に悪影響
必要なソフトやライセンスの未整備 → 法的・業務的リスク
一般職用のセキュリティ・通信制限 → 開発環境の自由度を阻害
このように、「一般職の延長線上」での設備設計では、専門職が本来の能力を発揮できる環境にはなりません。
成長支援とキャリア設計:専門職には「別の道筋」が必要
研修・キャリアパスも「職種別」に最適化すべき
一般職では、入社から数年のOJT、定期的な異動、昇進といった形で自然なキャリアパスが設計されています。しかし、専門職はスキルアップ・技術習得をベースにキャリアを築くため、同じ道筋は通用しません。
技術研修の機会がない → スキルの陳腐化・離職
評価制度が専門性を見ない → モチベーション低下
キャリアパスが不明瞭 → 長期的な定着が困難
たとえば「課長→部長」といった管理職路線が一般職には機能していても、専門職にとっては「技術的成長」や「スペシャリストとしての評価」が不可欠です。
企業が取るべきアクション:専門職の「異なる基準」を理解せよ
専門職と一般職は、業務内容も、評価軸も、求められる環境もまったく異なります。これを同じ土俵で扱おうとすること自体が、採用や定着の障害になります。
必要な対策
専門職専用の給与テーブルを設ける
→ 市場調査を基に、スキルと経験に見合った報酬設計
業務環境の整備を最優先する
→ PC、ツール、ネットワークなど専門職仕様での投資
学習・研修支援を制度化する
→ 資格支援、書籍購入補助、技術カンファレンスの参加支援
キャリアパスと評価制度を分けて設計する
→ 技術職には「技術成長」と「成果評価」の2軸で設計
採用時から待遇の透明性を高める
→ 給与・設備・研修の実態を明確に説明し、不安を解消
まとめ:職種ごとの差異を受け入れることが“戦力化”への第一歩
エンジニアやデザイナーは、一般職とはまったく異なるロジックで動く存在です。それは給与、環境、キャリアに至るまで一貫しています。
にもかかわらず、「全職種を同じ制度で管理する」ことで、企業はせっかくの採用チャンスを逃し、貴重な人材を失っています。
職種ごとの違いを認め、その違いに応じた制度・待遇を設けることが、専門職人材を“戦力化”するための第一歩です。
待遇改善を単なるコストではなく、未来への投資として捉え、専門職が活躍できる基盤を構築していきましょう。